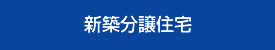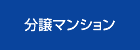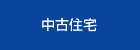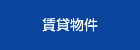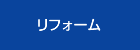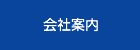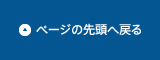「キッチンをすっきり片付けたい」「食材や日用品はまとめ買いする」、そんな方に人気のキッチンパントリー。
食品や日用品などをまとめて収納できる便利なパントリーですが、生活スタイルや扱い方によって最適なパントリーの形はさまざまです。
無計画につくってしまうと、かえって使いにくく、ムダなスペースとなってしまう可能性があるでしょう。
この記事では、パントリーのタイプや広さの目安、設置のメリット・デメリット、注意すべきポイントなども含めて、くわしく解説していきます。注文住宅や新築の購入などでキッチンづくりを検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
パントリーは主に3タイプ!特徴や広さを解説
キッチンパントリーには、大きく分けて「壁面タイプ」「ウォークインタイプ」「ウォークスルータイプ」の3種類があります。
使いやすい広さはパントリーのタイプによって異なりますが、おおまかな目安としては4人家族で1畳程度です。具体的な広さを検討する際は、収納する物の種類や大きさ、家族のライフスタイルにも配慮した計画が必要です。収納予定の物をリストアップして、効率的に収納できるスペースを確保しましょう。
ここでは、パントリータイプ別の特徴や一般的な広さについてくわしく紹介します。
壁面タイプ

キッチン背面など壁面に設置するタイプのパントリーは、限られたスペースでも効率的に収納力をアップできるのが魅力です。システムキッチンの一部として壁付けで設置されることも多く、調理中でもスムーズに食材や調味料を取り出せます。
サイズは幅90~180cm、奥行き45~60cm程度が一般的です。高さを調整できる可動棚を設けると、小さな調味料から高さのあるボトル類までサイズを問わずに収納できて活用しやすくなるでしょう。
また、設置場所に応じて取手や引き出しなどのデザインを工夫すれば、機能性と見た目の美しさを両立させられます。
ウォークインタイプ

個室型のウォークインタイプのパントリーは、1~2畳が一般的な広さで、食材や日用品のストック、調理器具などを大量にすっきり収納できます。まとめ買いが多い家庭や収納アイテムが多い方に特におすすめのタイプです。
キッチン奥の行き止まり部分に設けられるケースが多いため、出入りしにくくならないよう冷蔵庫の位置や扉の有無などを考慮しましょう。また、通路幅は最低でも人が一人通れる60cm程度を確保し、動きやすい空間を確保することが大切です。
棚の配置や高さも工夫すれば、より多くの物を収納できます。おしゃれな収納ボックスやラベルの活用により、見た目もすっきり整理整頓されたパントリーになるでしょう。
ウォークスルータイプ

出入り口が2方向にあるウォークスルータイプのパントリーは、キッチンと他の部屋をつなぐ動線上に設置することで、家事効率を格段に向上させられます。
一般的な広さは2~3畳程度で、人がすれ違えるよう通路幅は70cm程度確保しておくと良いでしょう。
キッチンと洗面室の間に設置すれば、料理をしながら洗濯をする「ながら家事」もスムーズに行えます。また、キッチンと玄関、もしくは勝手口の間に設置すれば、買い物帰りに持ち込んだ荷物をすぐに収納できるため、動線が短縮され便利です。
パントリーを設けるメリット・デメリット

パントリーの設置により得られるメリットは多くありますが、一方でデメリットがあることも事実です。うまく使いこなせなければムダなスペースになってしまう可能性もあるため、両方を理解したうえで、本当にパントリーが必要かどうかを検討しましょう。
メリット
パントリー最大のメリットは、キッチンをすっきり片付けられる点です。食材や調理器具、日用品などをまとめて収納できるため、食器棚やキャビネットを新たに設ける必要がなく、作業スペースを広々使えます。
近年人気のオープンキッチンはキッチン内が丸見えになってしまうデメリットがありますが、パントリーを活かせば生活感が出やすいアイテムを隠せるため、常に美しいキッチンを保てます。急な来客時にも慌てることなく対応できるでしょう。
また、必要な物がすぐに取り出せるため、調理の時間短縮にもつながります。さらに、まとめ買いした食品や飲料などを大量にストックできるため、買い物へ行く頻度を減らせる点も、忙しい共働き家庭や小さなお子様がいる家庭などにとって大きな魅力といえるでしょう。
デメリット
一方で、パントリーを設置するには、専用のスペースと費用が必要になります。限られた床面積の中で計画する場合、リビングや他の部屋の広さを削る必要が生じるかもしれません。また、設置費用には棚や扉、換気設備などが含まれるため、予算に応じた計画が重要です。
また、広いスペースを確保していても、収納物が整理されていない場合、かえって物が散乱しやすくなり管理が難しくなる可能性もあります。効率的に使用するためには、収納物に合わせた棚やラベリングなど、計画的な管理が求められます。
| ▶分譲住宅でも追加金なしで注文住宅のような自由度の高い家づくりができる! ヤング開発の『注文家創り』についてはこちら |
おすすめパントリー間取りアイデア6選
パントリーの間取りは、ライフスタイルや家の構造によってさまざまなバリエーションが考えられます。ここからは、おすすめの間取り実例を6パターン紹介します。
キッチン横や背面に設置

キッチンの隣や背面に設置するタイプのパントリーは、もっとも一般的なスタイルです。どんな家庭にも取り入れやすく、調理しながら食材や調味料などを取りやすいのがメリット。奥行きが浅くなりがちですが、天井高いっぱいまでのパントリーにすれば、スペースをムダなく活かせます。
キッチンの作業台から1~3歩程度で手が届く場所に配置すると、時間と手間が節約できて効率よく家事をこなせるでしょう。
また扉付きにすれば、たくさん物を収納してもすっきり見せられます。一方でオープンタイプを採用する場合は、棚受金物や棚板のデザインにこだわってみましょう。「見せる収納」を意識してディスプレイを考えると、おしゃれなキッチンになります。

キッチンと玄関(または勝手口)の間に設置

玄関や勝手口とキッチンの間にパントリーを設ければ、まとめ買いした食材や日用品、重い飲料水などを短い距離で収納できます。買い物帰りの動線がスムーズになり、重い荷物を運ぶ負担も軽減されるでしょう。外部からの視線を遮りつつ、生活感を隠せる点も魅力です。
特に、お米や土付き野菜といった食品、重い飲料水などを保管するのに適しています。ゴミの一次置き場としても活躍するでしょう。衛生面を考慮して通気性を確保できる設計にすると、さらに使いやすくなります。
キッチンと洗面室の間に設置

キッチンと洗面室の間に、通り抜けできるウォークスルータイプのパントリーを設ける間取りもおすすめです。
洗面室には洗濯機を置いている家庭も多いため、キッチンとつながる動線ができれば、料理しながらの洗濯といった「ながら家事」が可能になります。お子様の入浴中などすぐに様子を見に行けるのも便利な点です。
洗剤やタオルなどのストック、掃除用品なども一緒に収納できるため、収納場所を集約して家事効率を高められます。
ただし、洗面室の湿気がパントリーに流れ込んでしまう可能性があるため、換気対策をしっかり行いましょう。
階段下を活用

デッドスペースを活用して、階段下にパントリーを設置する方法もあります。パントリーのスペースを確保するためにリビングや玄関の面積を削りたくない、またはパントリーに充てる面積がない、というときにおすすめの間取りです。
ただし階段下の形状によっては、奥行きや高さが十分に確保できないこともあります。収納したい物のサイズと階段下のスペースを事前に照らし合わせておきましょう。
ワークスペースと兼用

パントリー内にカウンターを設置してワークスペースをつくれば、家事の合間に仕事したり、一息ついてコーヒータイムを楽しんだりするスペースとして活用できます。家族の気配を感じながらも、集中しやすく落ち着き感のある場所として重宝するでしょう。
また適宜コンセントを設ければ、パソコンや充電器などを使用する際にも便利です。作業しやすい明るさを確保する照明も忘れず設置しましょう。
| ▶おしゃれなキッチンをつくりたい方必見! ヤング開発の施工事例はこちら |
パントリー設計で後悔しないための注意点

理想的なパントリーをつくるためには、事前の計画が重要です。使いにくいパントリーになって後悔しないよう、事前に行っておきたいことと計画時の注意点を以下にまとめました。
・収納する物を事前にリストアップする
・動線を考慮する
・散らかりやすい場所には扉を設ける
・湿気対策を講じる
・収納アイテムのサイズや重さに合わせる
・コンセント位置を入念に計画する
それぞれ詳しく解説していきます。
収納する物を事前にリストアップする
パントリーには何を収納するのか、具体的にリストアップしておきましょう。
食材、調味料、調理器具、日用品など、カテゴリーごとに分けてリスト化すれば、必要なスペースや棚のサイズ、種類を正確に把握できます。これによりデッドスペースを最小限に抑え、効率的な収納計画を立てられます。
動線を考慮する
パントリーの設置場所やレイアウトは、日々の生活動線・家事動線を考慮して決めることが大切です。
例えば、頻繁に使用する食材や調味料は、キッチン作業台から手の届きやすい位置に配置すると、調理中の動きを最小限に抑えられます。
また、買い物帰りの動線を考えて、玄関からパントリーまでの距離を短くするのも効果的です。そのほかにも、料理と洗濯の同時進行、子守や在宅ワークしながらの片付けなど、ライフシーンに応じた動線を具体的にイメージしながら計画すると、使いやすいパントリーになるでしょう。
散らかりやすい場所には扉を設ける

大小さまざまな物を収納するパントリーは、常に整理しておかなければごちゃごちゃと散らかりがち。いつでもキッチンをきれいに見せたいという方には、扉付きのパントリーがおすすめです。
扉付きパントリーは開き戸タイプが一般的ですが、引き戸タイプなら開け閉めの際に通路の邪魔にならず出し入れもしやすいメリットがあります。
ただし、使用頻度の高い調味料や家電などを置く場所は、逆にオープンタイプにすることで使い勝手がアップします。扉の有無は、収納物やライフスタイルに合わせて検討しましょう。
換気設備を設ける
パントリーには食材や日用品を収納するため、適切に換気を行う必要があります。
特に、湿気がこもりやすいウォークインタイプのパントリーや長期間保存する食材が多い場合には、換気扇や通気口を設置して常に新鮮な空気が流れるようにしましょう。
大きな窓は紫外線や日射熱の影響で収納物を劣化させる恐れがありますが、スリット窓や小窓であれば適度な通風と明るさを確保するのに最適です。間取りに応じて採用を検討しましょう。
さらに、除湿剤や乾燥剤を置いたり、定期的に扉を開放して空気の入れ替えを行ったりするのも効果的です。湿気はカビや食品の劣化の原因になるため、十分な対策を行いましょう。
収納アイテムのサイズや重さに合わせる
収納するアイテムのサイズや重さに合わせて棚の高さや奥行き、種類を調整しましょう。
例えば奥行きについて、調味料や小さなアイテムは浅めの棚、大きな調理器具や家電は深めの棚が適しています。
可動棚は収納物に合わせて棚の高さを変えられるメリットがありますが、重い物や家電など安定感が必要な物を収納する場合は固定棚の方が適しています。棚板の素材や厚み、棚受金物によっても支えられる重さは変わるため、重い物を置く場合は必ず耐荷重を確認しましょう。
また、収納量が増えることも想定して、ある程度の余裕を持たせた設計が大切です。
コンセント位置を入念に計画する
「パントリーにコンセントが必要なの?」と思われる方もいるかもしれませんが、パントリー内は意外にコンセントが重宝します。
パントリー内にコンセントがあると、家電の充電、換気、照明設置など、さまざまな用途に活用できるからです。
例えば、近年増加しているコードレス家電の充電や、調理中に使用するスマートフォンやタブレットの充電ができるようになります。また、サーキュレーターや空気清浄機などの換気機器を使用できれば、パントリー内のニオイ対策や湿気対策にも役立つでしょう。特に、精米機やワインセラーなどを置く予定のあるご家庭では、コンセントの設置は必須です。
使用する物に応じて高さなど使いやすい位置を検討し、後にタコ足配線とならないよう入念に計画しましょう。
まとめ|使いやすいパントリー計画で理想のキッチンを!
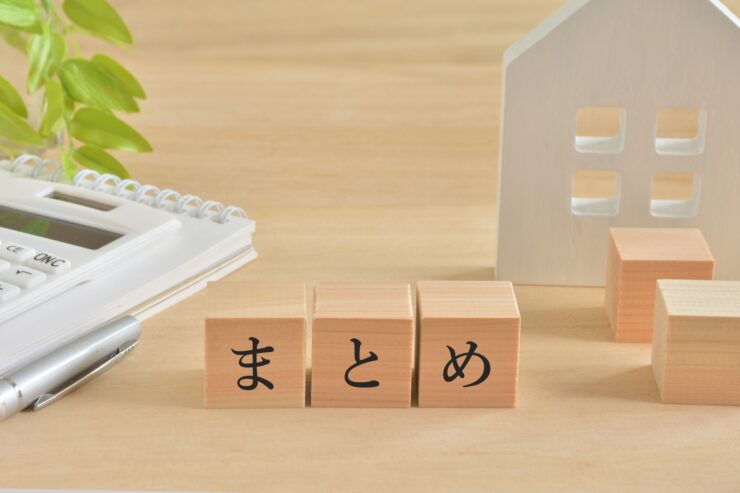
今回は、キッチンパントリーの種類、広さ、メリット・デメリット、間取り実例、設計上の注意点など、さまざまな情報をお伝えしました。
使いやすいパントリーをつくるためには、収納する物、使い方、家事動線などを事前にしっかりと考えて計画することが大切です。
この記事を参考に、あなたの生活スタイルに合った理想のキッチンパントリーを実現してください。
ヤング開発では、分譲住宅でもデザインや設備が選べる『注文家創り』を展開し、お客様のライフスタイルを考慮しながら快適で暮らしやすい間取りをご提案します。
兵庫で家づくりをご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
2025年4月 (9)
2025年3月 (8)
2025年2月 (11)
2025年1月 (10)
2024年12月 (11)
2024年11月 (10)
2024年10月 (10)
2024年9月 (9)
2024年8月 (10)
2024年7月 (9)
2024年6月 (12)
2024年5月 (21)
2024年4月 (9)
2024年3月 (8)
2024年2月 (8)
2024年1月 (9)
2023年12月 (9)
2023年11月 (8)
2023年10月 (10)
2023年9月 (10)
2023年8月 (8)
2023年7月 (8)
2023年6月 (10)
2023年5月 (7)
2023年4月 (9)
2023年3月 (9)
2023年2月 (9)
2023年1月 (9)
2022年12月 (11)
2022年11月 (8)
2022年10月 (8)
2022年9月 (9)
2022年8月 (7)
2022年7月 (8)
2022年6月 (7)
2022年5月 (8)
2022年4月 (8)
2022年3月 (8)
2022年2月 (8)
2022年1月 (8)
2021年12月 (8)
2021年11月 (7)
2021年10月 (7)
2021年9月 (8)
2021年8月 (8)
2021年7月 (8)
2021年6月 (8)
2021年5月 (8)
2021年4月 (8)
2021年3月 (7)
2021年2月 (8)
2021年1月 (8)
2020年12月 (8)
2020年11月 (8)
2020年10月 (7)
2020年9月 (8)
2020年8月 (8)
2020年7月 (8)
2020年6月 (8)
2020年5月 (9)
2020年4月 (8)
2020年3月 (8)
2020年2月 (8)
2020年1月 (8)
2019年12月 (8)
2019年11月 (8)
2019年10月 (8)
2019年9月 (8)
2019年8月 (8)
2019年7月 (8)
2019年6月 (8)
2019年5月 (8)
2019年4月 (8)
2019年3月 (8)
2019年2月 (8)
2019年1月 (8)
2018年12月 (7)