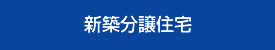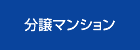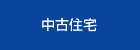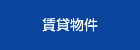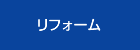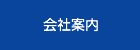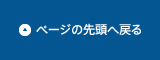住宅の購入や建築を考える際、重要なポイントのひとつが「断熱性能」です。一年中快適で過ごしやすく、光熱費が安い家をつくるためには、適切な断熱が欠かせません。
この記事では、住宅の断熱性能を評価する指標である「断熱等級」について詳しく解説します。さらに、2022年に新たに設けられた断熱等級5・6・7や、2025年度以降に義務化される等級についても紹介します。
「断熱等級の情報を知りたい」「断熱性が高い家に住みたいけれど、どのレベルが正解か分からない」とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
住宅の「断熱等級」とは?基準はある?

まずは「断熱等級」について、その概要や等級レベルの違い、基準を詳しく解説していきましょう。
断熱等級の概要と確認方法

断熱等級は正しい名称を「断熱等性能等級」といい、2000年施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく「住宅性能表示制度」で評価される項目のひとつです。住宅性能表示制度は、10分野32項目に分けられた住宅性能を第三者機関が客観的に評価し、購入者などに分かりやすく示す「住宅の通知表」ともいえる存在です。
断熱等級は等級1~7の7段階に分けられ、数字が大きいほどに建物の断熱性が高いことを示します。
住宅性能表示制度では認定後に「住宅性能評価書」が交付され、断熱等級は「温熱環境に関すること」という分野内の項目として、その等級を確認できます。
住宅性能評価書を取得する方法は、以下のとおりです。
| 注文住宅 | 設計図書に基づき、建築前に「設計住宅性能評価」を、完成後に「建設住宅性能評価」を取得します。依頼先は登録住宅性能評価機関です。建築会社が代行してくれるケースが一般的です。 |
| 建売・分譲住宅 | すでに建設住宅性能評価を取得済みの物件もあります。評価書の内容を確認しましょう。取得済みでない場合は、売主(不動産会社)に問い合わせてください。 |
| 中古住宅 | 既存住宅状況調査技術者が作成する「既存住宅状況調査報告書」と、建築士が作成する「評価書」に基づき、「既存住宅性能評価」を取得します。依頼先は登録住宅性能評価機関です。売買時に仲介を行う不動産会社に相談してみましょう。 |
断熱等級1~7の違い

断熱等級は、制度が開始した2000年当初では1~4の等級が設けられていましたが、その後の2022年には等級5~7が追加されています。
各等級の違いは以下の通りです。
【断熱等級の施行年月と内容】
| 断熱等級 | 施行年月 | 内容 |
| 等級1 | - | 昭和55年 旧省エネ基準未満(無断熱) |
| 等級2 | 2000年4月 | 昭和55年 旧省エネ基準 |
| 等級3 | 平成4年 新省エネ基準 | |
| 等級4 | 平成28年 次世代省エネ基準 | |
| 等級5 | 2022年4月 | 「ZEH」と同水準 |
| 等級6 | 2022年10月 | 「HEAT20 G2」とおおむね同水準 |
| 等級7 | 「HEAT20 G3」とおおむね同水準 |
ちなみに、2021年に国土交通省が公表した資料(※)では、断熱等級4に相当する断熱性能を持つ住宅は全国でたった13%という結果でした。9割近くの住宅は断熱等級3以下の水準で、約3割は断熱等級1の無断熱に相当する低レベルの性能であることが判明しています。
十分な断熱性能を持たない住宅は、快適性が低く冷暖房効率が悪いだけでなく、健康被害や住宅寿命低下のリスクも抱えます。今後住宅購入を検討するならば、断熱性能は特にこだわるべき要素といえるでしょう。
※出典:2021年国土交通省 社会資本整備審議会 建築分科会資料
断熱等級における地域別の基準値「UA値」

断熱等級の評価には、「UA値」という基準値が用いられます。
UA値は「外皮平均熱貫流率」のことで、室内から屋外への熱の逃げやすさを示す数値です。
外皮(屋根・外壁・床・窓など)を伝って室内から逃げる熱の量を、外皮面積で割り算出するため、UA値が小さいほどに熱が逃げにくく、断熱性能および省エネ性能が高いことを示します。
日本はエリアによる気温差が激しいため、断熱等級の基準となるUA値は8つに分けられたエリアごとに設定されています。各エリアの数値は以下の通りです。
【地域区分別 断熱等級とUA値】
| 地域区分と主要都市 | ||||||||
| 1 旭川 | 2 札幌 | 3 盛岡 | 4 仙台 | 5 宇都宮 | 6 東京・大阪 | 7 鹿児島 | 8 那覇 | |
| 等級1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 等級2 | 0.72 | 1.21 | 1.47 | 1.67 | 2.35 | - | ||
| 等級3 | 0.54 | 1.04 | 1.25 | 1.54 | 1.81 | - | ||
| 等級4 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | - | |||
| 等級5 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | - | ||||
| 等級6 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | - | ||||
| 等級7 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | - | ||||
参考:国土交通省|省エネ性能表示制度 ラベル項目の解説「断熱性能」
例えば、6地域に該当する東京や大阪のエリアにて断熱等級4をクリアするためには、UA値0.87以下の断熱性能を持つ住宅であることが求められます。
UA値を下げる(断熱性能を高める)方法
UA値を下げるには、断熱材、窓、気密性、日射遮蔽、4つの要素の性能・精度を高めることがポイントです。
断熱材は、密度が高く厚みがあるほどに断熱性能を高められます。グラスウール、ロックウール、セルロースファイバー、ウレタンフォームなど種類も豊富ですが、施工性や湿気への強さ、価格帯などを考慮し、床・壁・天井それぞれに適した素材を用いることが大切です。
窓は、複層ガラスやLow-E複層ガラスを採用することで断熱性を高め、サッシに熱伝導率が低い樹脂サッシや木製サッシを用いれば、さらに効果を高められます。窓の面積を小さくしたり、北側の窓の数を減らしたりすることも有効です。
気密性を高めるには、建物の隙間を塞ぐ気密施工を行い、計画換気システムとの組み合わせにより換気による熱損失を抑えます。
日射遮蔽では庇や軒の出を活用し、夏は日射による熱を抑え、冬は逆に日射により室内を暖めます。家の形状は正方形に近く、外皮面積を小さくすることでUA値を下げられます。
断熱等級と省エネ等級の違い
断熱等級とよく間違われやすい用語に「省エネ等級」があります。断熱等級と省エネ等級はどちらも住宅性能の指標ですが、評価対象が異なります。
断熱等級は建物外皮の断熱性能のみを評価するのに対し、省エネ等級は断熱性能に加え、冷暖房や給湯、照明など住宅で消費する全エネルギー量(一次エネルギー消費量)も評価対象です。省エネ等級は断熱等級と一次エネルギー消費量等級を組み合わせた総合指標で、等級1~7で評価されます。
つまり、省エネ等級は、設備のエネルギー効率や太陽光発電など創エネルギー設備の導入状況も考慮した、より包括的な指標です。
高断熱でもエネルギー消費の多い設備を使えば省エネ等級は低く、断熱性は低くても太陽光発電などでエネルギー消費を大幅削減すれば省エネ等級は高くなる可能性があります。住宅購入時は両者を理解し、ライフスタイルや考え方に合った住宅を選びましょう。
2022年に新設された断熱等級5・6・7

断熱等級新設の背景と目的
住宅性能表示制度が施行されたのは2000年ですが、断熱等級は1979年の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」により定められた省エネ基準が反映されていました。
政府は、2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、省エネ法を段階的に改正しています。
これらを背景に、2022年4月に断熱等級5が、同年10月には断熱等級6・7が新設されました。
「ZEH」水準の等級5、「HEAT20」水準の等級6・7
断熱等級5は、政府が補助金制度などを設けて推し進める「ZEH(ゼッチ)」相当の断熱性能です。さらに、断熱等級6・7は国際的にも劣らない断熱基準として注目されている「HEAT20」のG2・G3に相当する性能です。政府がスピード感を持って断熱に関する制度の改正を進めていることもあり、今後建てられる住宅は、現在の一般住宅に比べ断熱性・省エネ性が飛躍的に進化していくでしょう。
| ▶無料標準で選択可!ZEHを超える断熱性能! ヤング開発の『断熱等級6(HEAT20 G2グレード仕様)』についてはこちら |
2025年度以降は断熱等級4への適合が義務化
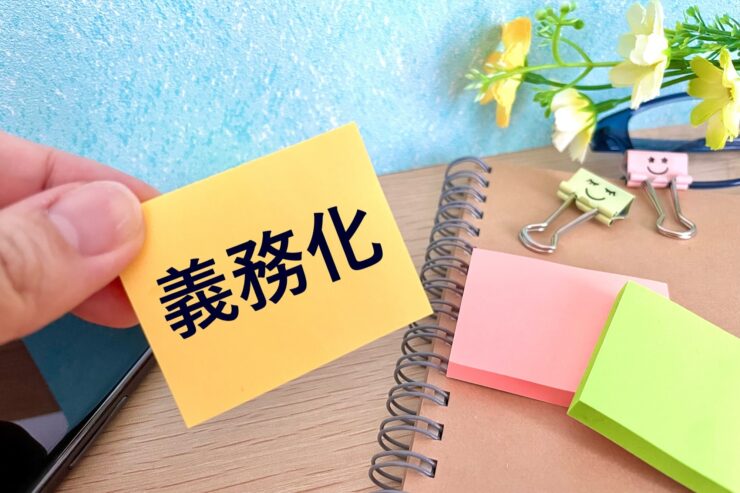
断熱等級4が義務化される理由
2022年6月に公布の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」をもとに、建築物省エネ法が改正されました。
これにより、2025年4月からすべての新築住宅・非住宅において、省エネ基準への適合が義務化されます。
2024年度までの制度で省エネ基準への適合が義務付けられているのは、非住宅で床面積300㎡以上の中・大規模の建物のみ。中・大規模の住宅では「届出」義務が、それ以外の小規模住宅と非住宅は「説明」義務が課せられています。
省エネ基準における断熱性能では、断熱等級4以上が要件となっています。今後は住宅を含むすべての建物に省エネ基準適合が義務化されることで、2022年までは最高レベルであった断熱等級4が、一転して最低レベルの断熱性能になるのです。
さらに、2030年度以降は断熱等級5以上が義務化予定となっており、住宅の断熱性能は今後ますます強化される見通しです。
義務化による消費者への影響は?
2025年4月からの省エネ基準適合義務化は、新築住宅の性能を大きく底上げします。
これまで多くの住宅で断熱性能の低さが課題でしたが、義務化により最低でも断熱等級4相当が確保され、快適性アップ、光熱費負担の軽減、CO2排出量削減といった効果が期待できるようになります。室内の温度差に起因するヒートショックといった健康被害も大きく減少するでしょう。
一方で、義務化は建築コストの上昇を招きます。断熱材の強化や高性能窓サッシの採用など、建築資材や工事費用が増加するだけでなく、設計・施工の難易度上昇による人件費増加も懸念されます。結果として、住宅価格に反映され消費者の負担増につながる可能性は否定できません。
しかし、将来的に初期投資の増加分を光熱費削減で回収できる見込みは十分にあります。高断熱住宅は、冷暖房効率が高いためランニングコストを抑えられ、住宅の長寿命化によりメンテナンスコストを削減できるなど、長期的な経済的メリットが期待できます。
消費者は、建築コストと光熱費削減効果のバランス、健康面・環境面への配慮を総合的に判断し、住まいを選択することが大切です。
これから家を購入する際におすすめの断熱等級は?
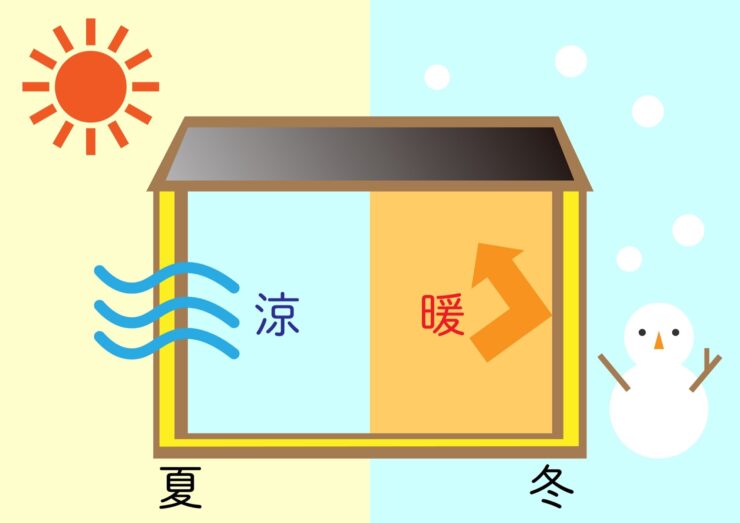
最低でも等級5、理想は等級6以上を目指して
2025年は断熱等級4が、2030年には断熱等級5が義務化されることを考えれば、数年先に国の最低レベルとなる性能は確保しておきたいところ。これから家を建てるならば、断熱等級5以上の性能が望ましいでしょう。
断熱等級5は、省エネ住宅で言うところのZEH住宅や長期優良住宅に相当する断熱性能です。冬の寒さや夏の暑さを感じにくく、確かな断熱性を感じられるでしょう。太陽光発電システムなどを組み合わせれば、光熱費の大幅な削減も見込めます。
ただし、より温度差の少ない快適性や省エネ性を感じたいのであれば、等級6相当の「HEAT20 G2」グレード以上の性能を検討しましょう。
HEAT20 G2グレードは、断熱等級6相当の性能であり、G3グレードは断熱等級7相当の性能です。HEAT20 G2グレードであれば、2025年度から義務化される平成28年省エネ基準と比較して約35~60%省エネルギーになるほか、冬季でも室内温度が13度を下回らない快適性を手に入れられます。
初期費用は高くなりますが、長い目で見れば光熱費を抑えられ、健康にも良い住まいを実現できるでしょう。生涯のランニングコストや健康面でのメリットを考慮すると、十分に検討する価値があります。
| ▶無料標準で選択可!ZEHを超える断熱性能! ヤング開発の『断熱等級6(HEAT20 G2グレード仕様)』についてはこちら |
まとめ|ヤング開発なら高断熱の「HEAT20 G2」グレードが無料標準!

2025年度以降は断熱等級4以上が義務化されることもあり、家の断熱性能への注目度はさらに高まっていくでしょう。
断熱性が高い家は、快適性や省エネ性がアップし、光熱費削減や健康リスクの低下につながります。
今後の家づくりを検討するならば、2030年に義務化が予定されている等級5を超える性能を確保するのがおすすめです。
また、断熱性能の強化が急ピッチで進められている昨今では、住宅会社によって断熱性能に対する理解度や施工精度にムラが生じているのが現状です。断熱性にこだわってマイホームの購入を検討するなら、住宅性能評価書の取得や省エネ住宅施工に関する実績が豊富な住宅会社を選びましょう。
兵庫で家づくりを手掛けるヤング開発は、ZEHビルダーの先駆け的な存在として高断熱住宅の施工を数多く行ってきました。現在提供する住宅は、全戸ZEH仕様が標準となっているだけでなく、さらに選べる無料標準として、断熱等級6に相当する「HEAT20 G2」グレードを設定しています!通常は高額な追加費用が必要な高断熱住宅も、ヤング開発であれば標準仕様の範囲で実現可能です。
超高性能断熱材やLow-Eペアガラスの樹脂サッシ窓、高断熱「D2」仕様の玄関ドアなどを標準装備し、外気温の影響を受けにくい高気密高断熱の家づくりを叶えます。
1年中快適で光熱費の心配がない高断熱住宅なら、ヤング開発にぜひお任せください。
2026年1月 (4)
2025年12月 (10)
2025年11月 (10)
2025年10月 (10)
2025年9月 (10)
2025年8月 (10)
2025年7月 (10)
2025年6月 (10)
2025年5月 (10)
2025年4月 (9)
2025年3月 (8)
2025年2月 (11)
2025年1月 (9)
2024年12月 (11)
2024年11月 (9)
2024年10月 (10)
2024年9月 (8)
2024年8月 (10)
2024年7月 (9)
2024年6月 (11)
2024年5月 (19)
2024年4月 (9)
2024年3月 (8)
2024年2月 (7)
2024年1月 (9)
2023年12月 (9)
2023年11月 (8)
2023年10月 (10)
2023年9月 (10)
2023年8月 (8)
2023年7月 (8)
2023年6月 (10)
2023年5月 (7)
2023年4月 (9)
2023年3月 (9)
2023年2月 (9)
2023年1月 (8)
2022年12月 (11)
2022年11月 (8)
2022年10月 (8)
2022年9月 (8)
2022年8月 (7)
2022年7月 (8)
2022年6月 (7)
2022年5月 (8)
2022年4月 (8)
2022年3月 (8)
2022年2月 (8)
2022年1月 (8)
2021年12月 (8)
2021年11月 (7)
2021年10月 (7)
2021年9月 (8)
2021年8月 (8)
2021年7月 (8)
2021年6月 (8)
2021年5月 (8)
2021年4月 (8)
2021年3月 (7)
2021年2月 (8)
2021年1月 (8)
2020年12月 (8)
2020年11月 (8)
2020年10月 (7)
2020年9月 (8)
2020年8月 (8)
2020年7月 (8)
2020年6月 (8)
2020年5月 (9)
2020年4月 (8)
2020年3月 (8)
2020年2月 (8)
2020年1月 (8)
2019年12月 (8)
2019年11月 (8)
2019年10月 (8)
2019年9月 (8)
2019年8月 (8)
2019年7月 (8)
2019年6月 (8)
2019年5月 (8)
2019年4月 (8)
2019年3月 (8)
2019年2月 (8)
2019年1月 (8)
2018年12月 (7)