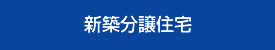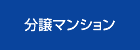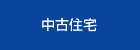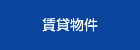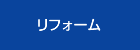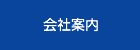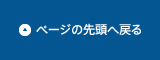こんにちは、ヤング開発です。
戸建て住宅の階段は、一昔前まで玄関ホールや廊下に配置するのが一般的でしたが、最近ではおしゃれなデザインの階段や配置のバリエーションが増え、あらゆるパターンから選択できるようになりました。
上下階をつなぐ役割だけでなく住まいを彩るアクセントとしても、階段にこだわりたいという方が多いのではないでしょうか。

今回は、階段の種類や配置を実例とあわせて紹介します。
マイホームのアイデアをお探し中の方は、ぜひ参考にしてくださいね。
●インテリアのアクセントになる「オープン階段」

踏板と骨組みのみでつくられるオープン階段(スケルトン階段)は、階段がインテリアのアクセントとなりおしゃれな空間づくりができると人気のデザインです。
おしゃれなだけでなく、室内が開放的で広々とした印象になるのもメリットのひとつです。
●家族コミュニケーションがはかどる「リビング階段」

リビング内に階段を設けるリビング階段は、LDKから2階への移動がしやすく、家族で顔を合わせる機会が増えるメリットがあります。
ただし、2階の暑さ寒さがリビングに伝わりやすい特性もあるため、しっかりと断熱性を高め温度差の少ない家にすることが重要です。
●テレワークスペースにも最適な「スキップフロア付き階段」

階段の中ほどにスキップフロアを設ける間取りであれば、限られた空間を広く使えます。
空間全体がゆるやかにつながるため、家族がそれぞれの場所で過ごしていても気配を感じられる程よい距離感が得られます。
テレワークスペースとして、趣味スペースやお子様の遊び場として、柔軟に使える魅力的な空間になるでしょう。
新築住宅を建てるなら、階段にもこだわることで空間の充実度は格段にアップします!
生活動線やインテリアの統一感へ考慮しながら、種類や素材、配置を検討してみてくださいね。
ヤング開発では、分譲住宅でもご希望の間取りやデザインを実現する「注文家創り」を展開しています。
こだわりの家づくりなら、ヤング開発におまかせください。
こんにちは、ヤング開発です。
今回は、徒歩10分圏内にあらゆる施設が揃うプレミアムな立地が自慢の「ローズビレッジ宝殿駅前レジデンス」をご紹介します。

「ローズビレッジ宝殿駅前レジデンス」は、JR宝殿駅まで徒歩8分の近さ!
新快速停車駅であるJR加古川駅までわずか1駅のため、都心部への通勤・通学も楽々です。
また、スーパーやドラッグストア、100円ショップや多彩な飲食店が揃う大型ショッピングセンター「アイモール高砂」までは、たったの徒歩3分!
日々のお買い物から週末の外食まで、いつでも便利にご利用いただけます。

ホームセンターやコンビニ、人気の業務スーパーなどへも徒歩10分以内で到着できるため、買い物に困ることなく充実した生活が送れます♪
また、緑豊かな大型公園「高砂総合運動場」までは徒歩7分。
お子様とのアクティビティや、ちょっとした散歩、運動などにもおすすめのスポットです。

さらに、保育園と小学校へも徒歩9分内という近さだから、送り迎えしやすく、お子様の通学も安心して見守れます。
子育てしやすい充実の住まい環境を実感していただけるはず♪

日々の暮らしに欠かせない医療施設や金融機関も、自転車や自動車を使わなくても行ける距離に複数揃っています。
緊急時や体調不良の時でも身近に病院があると安心できますね。

「ローズビレッジ宝殿駅前レジデンス」は、絶好の充実環境にもかかわらず、平均敷地面積約45坪とゆとりの広さを確保しています。

ぜひご家族全員で現地を訪れて、新しい生活のイメージを膨らませてみてくださいね♪
ヤング開発では現在、光熱費が0に近づくZEHと保険料が割安になる省令準耐火構造が全戸で無料標準!
さらに、夏の大感謝祭開催中につき、ZEHを超える断熱性能の「HEAT20・G2グレード」仕様またはIoT住宅仕様のいずれかお好きなほうをお選びいただけます。
注文家創りは定価50万円までのオプション付き、完成モデルはカーテンや照明器具、エグゼクティブ意匠付きとなっています。
WEBから見学予約の上、ご来場いただいた方には、3000円分のQUOカードをプレゼント!
※アンケートにお答えいただいた1組1家族様1回限り。なくなり次第終了。
詳しくは「ローズビレッジ宝殿駅前レジデンス」公式WEBサイトをご確認ください!
https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/4takasago/rv_houdenekimae-residence/
▼見学予約フォームはこちら▼
https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/4takasago/rv_houdenekimae-residence/reserve/
▼資料請求はこちら▼
https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/4takasago/rv_houdenekimae-residence/contact/
少しでもご興味がございましたら、ぜひお気軽に現地をご見学くださいね!
※本記事は2024年6月現在の情報に基づいて作成されたものです。
各分譲地の最新情報につきましては、公式HPをご確認ください。

住宅の購入にあたり、断熱性能にこだわりたいという方も多いでしょう。
政府はこれまで段階的に住宅の断熱性・省エネ性に関する法規制を施行し、2025年には高性能住宅(断熱等級4以上)を義務化することを決定しています。その影響もあり、近年の家づくりでは断熱性能が特に注目され、間取りや耐震性などと並び重要な要素として捉えられるようになってきました。
そこで今回は、なぜ国を挙げて対策するほど住宅の断熱性能が重要なのか、あらためてそのメリットや基準をお伝えします。さらに、家づくりで今後目指すべき断熱等級の目安についても解説します。マイホームの購入をご検討の方は、ぜひ参考にしてください。
快適性だけじゃない!家の断熱性が重要な理由とは?

断熱性能は外部の熱が室内に入らないよう遮断する能力を指し、高性能な断熱材や窓サッシを使用することで、その性能を高めることができます。
「断熱性能が高い家」と聞くと、多くの方は「夏の暑さや冬の寒さの影響を受けにくい快適な家」をイメージするのではないでしょうか。
家の断熱性が影響するのは快適性だけではありません。重大な健康被害から住人を守る役割や、環境負荷の抑制といった効果も期待できます。それぞれ詳しく解説します。
健康被害から家族を守る

家の断熱性能を高めることで、主に以下2つの健康被害のリスクを大きく減らすことができます。
・ヒートショック
・アレルギーや喘息
急激な温度差が血圧を激しく変動させるヒートショックは、特に冬場に発生することが多く、毎年交通事故を大きく超える死亡者数が発表されています。
また、断熱性の低い家では外気に接する部分と室内温度との差が大きく、結露が発生しやすい環境になります。湿った空気や結露はカビを発生させ、深刻なアレルギーや喘息につながることも少なくありません。
ちなみにWHO(世界保健機関)では、住まいの断熱性が高いと呼吸器系疾患や心血管疾患、風邪やインフルエンザのリスクを低下させるとして、冬季における室温18℃以上を「強く勧告」しています。
消費エネルギーを抑える

外気温の影響を受けにくい高断熱の家とは、すなわち室内の温度を外に逃しにくい家です。
断熱性が高ければ高いほど冷暖房効率が上がり、少ない電力消費でも快適な温度を保ちやすくなります。また、高断熱化による省エネの促進は政府が一番に目的とする内容であり、その実現のためにあらゆる法整備や補助金事業を施行してきました。
省エネ化の実現は、住人にとっては光熱費の大幅な節約が叶い、地球規模で見ればCO2排出を減らし環境負荷を抑えるメリットがあります。
室内の温度差を減らす

戸建て住宅で暮らしたことがある方なら、冬の浴室で震えるような寒さを感じたり、夏に1階から2階に上がったときにムワッとした暑さを感じたりなど、不快な温度差を経験した方も多いのではないでしょうか。
高断熱の家では、室内の温度差を減らし一定に保つ効果が期待できます。地域や断熱性能にもよりますが、1台のエアコンで家中を快適な温度に保つことも可能です。寒さや暑さが厳しい季節でも、家の中での動きがスムーズになり稼働性も増すでしょう。
さらに、上下間の温度差も少なくなるため、足元からくる底冷えも感じにくくなります。
断熱性能を表す基準値

断熱性能を決定する要素に「UA値」という基準値があります。
この基準値は、住宅の外皮(天井・外壁・床・窓など)性能を表す指標です。家の断熱性能を表すときに必ず用いられるため、概要を把握しておくと良いでしょう。
熱の逃げにくさを示す「UA(ユー・エー)値」
UA値は「外皮平均熱貫流率」のことで、住宅内外の熱の出入りのしやすさを示します。
外皮を伝って室内から逃げる熱の量を、外皮面積で割ることで算出するため、UA値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能が高いことを示します。
家の断熱性能は「断熱等級」でチェック!

住まいの断熱性能は、住宅1軒ごとに判定された「断熱等級」により確認できます。
断熱性能の判断基準となる等級について、解説していきます。
断熱等級とは

断熱等級は正しい名称を「断熱等性能等級」といい、2000年に施行された品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)で定められた、住宅の断熱性能を示す等級です。
断熱等級は、等級数が大きいほど断熱性能が高いことを意味します。当初は等級4が最高でしたが、2022年に等級5~7が新設されました。
なお、2025年度以降の新築住宅は等級4以上、2030年度以降では等級5以上の義務化が決定しています。ただし義務化の施行に先立ち、【フラット35】や住宅ローン減税では、断熱等級4以上やエネルギー消費基準のクリアが利用条件となっています。断熱等級4は、すでに新築住宅でのスタンダードレベルと言えるでしょう。
目指すべきは断熱等級5以上

2025年度以降は断熱等級4以上が義務化されるため、家を建てる際はこの水準であれば良いのかといえばそうではありません。まもなく等級4は家づくりにおける最低レベルの断熱性能になり、さらに2030年には等級5が最低基準となります。
何十年と住まい続けるならば、少なくとも数年後に予定される最低基準は超えるべきです。等級5は、省エネ住宅で言うところのZEH住宅や長期優良住宅に並ぶ断熱性能です。
ただし、住まいの快適性や省エネ性をしっかりと実感したいのであれば、等級6以上相当の「HEAT20 G2」グレードを目指すことをおすすめします。
▼「HEAT20 G2」グレードについて、詳しくはこちら▼
省エネ重視なら「HEAT20 G2」! 家づくりで目指すべき断熱性能について解説
まとめ

今後は新築住宅において一定の断熱基準クリアが必須となることもあり、家の断熱性能への注目度はさらに高まっていくでしょう。
断熱性の高い住まいは、快適性や省エネ性がアップし、住む人の健康や地球環境を守ります。
法制度により段階的に高性能レベルが追加されてきた断熱等級ですが、今後の家づくりでは2030年に義務化が予定されている等級5を超える性能を確保することがおすすめです。
また、断熱性能強化が急ピッチで進められている今、住宅会社によって省エネ住宅に対する理解度や施工精度にムラがあるのが現状です。断熱性にこだわってマイホームの購入を検討するならば、省エネ住宅に関する実績が豊富な住宅会社を選びましょう。
兵庫において家づくりを手掛けるヤング開発は、ZEHビルダーとして先駆け高断熱住宅の施工を数多く行ってきました。現在提供する住宅では、すべてZEH仕様を無料標準としています。さらに選べる標準仕様として、断熱等級6に相当する性能の「HEAT20 G2」グレードを設定!
1年中快適に過ごせる高断熱住宅なら、ヤング開発にぜひお任せください。
▼ヤング開発の「HEAT20 G2」グレードについてはこちら▼
https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/company_blog/ヤング開発の断熱性能がグレードアップ!「heat20%e3%80%80g2/
こんにちは、ヤング開発です。
弊社は、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)補助事業のZEHビルダーに登録しています。
そしてこの度、2023年度のZEHビルダー評価制度において、最高ランクである6つ星(★★★★★★)ビルダーに認定されました!

2022年度に続き2年連続の6つ星獲得となります♪
「ZEHビルダー評価制度」とは、断熱性能が高くエネルギー消費量の少ない設備を備えた省エネ性能に優れたZEH住宅について、建築実績や建築目標の達成率を評価する制度です。
●ZEHビルダー評価制度とは?
ZEH(ゼッチ)住宅は、「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略で、エネルギー消費を抑えながら、太陽光発電などでエネルギーをつくり出し、年間のエネルギー消費を実質ゼロ以下にする省エネ住宅のことです。
ZEHビルダー評価制度は、ZEH住宅の家づくりにおける実績や普及への取り組みを評価する制度です。
「一般社団法人環境共創イニシアチブ」が毎年度公募・評価し、その結果を翌年度に公表しています。
●「6つ星」獲得はわずか9.7%!
2023年度の全国累計ZEHビルダー/プランナー登録数は5,738社ですが、その中で最高ランク6つ星の評価を得たのは558社と、全体のわずか9.7%でした!
6つ星を獲得するためには、ZEH実績の報告や自社ホームページへの表示のほか、受注した住宅の75%以上がZEH住宅、といった条件を満たさなければなりません。
●ヤング開発ではZEH住宅が全戸で標準仕様
ヤング開発は、全国的にも数少ない全戸ZEH住宅を標準仕様とする住宅会社です。
追加費用が不要で、最高峰のZEH住宅のマイホームが実現します。
さらに現在は、ZEH仕様のさらに上を行く断熱性能を誇る「HEAT20 G2」が無料標準で選択可能!

今後もヤング開発は、ZEH住宅および省エネ住宅のトップランナーとして、高性能でエコな家づくりの普及促進に邁進します。
家計や地球環境に優しく、一年中快適に暮らせる住まいにご興味をお持ちの方は、ぜひヤング開発までお気軽にご相談ください。
こんにちは、ヤング開発です。
今回は、当社分譲地「ローズビレッジ宝殿駅前Ⅵ」のモデルハウスの間取りをご紹介します。

【間取りポイント1】
洗面室は一般的なサイズを大きく上回る面積で、洗濯機や収納棚を置いても余裕たっぷりの広々空間!
室内干しができる枕棚パイプを設けているため、雨の日でも安心して洗濯ができます。

さらに、出入口はキッチン側と玄関側の2箇所に設置。
2way動線で、家族の出入りとぶつかることなく家事もスムーズに行えます。
【間取りポイント2】
キッチンには、多彩な収納を4箇所設置しました!
① 扉付き収納:ラップやキッチンペーパーのストック
②キャビネット:食器や調理家電
③パントリー:食品や日用品のストック
④床下収納:非常食や保存食

たくさん収納があるから、物があふれがちなキッチンもすっきり片付きやすく、いつでもキレイに保てます♪

【間取りポイント3】
お子様のお昼寝スペースや遊び場、家事スペースとして活躍する和室は、キッチン横に配置しました。
料理中でもお子様の様子を確認しやすくいつでも安心♪
家事の合間に一息つく憩いのスペースにもピッタリです。

【間取りポイント4】
家の中央に位置する階段は、人気のリビング階段を採用しました。
2階の個室に行く際も必ずリビングを通るため、家族と顔を合わせる機会が必然的に増え、コミュニケーションが取りやすい環境が生まれます。

室内温度が保たれやすい高断熱仕様の家なので、階段からリビングへ冷気や暖気が出入りする心配も少ないのがポイントです♪

家事楽動線や豊富な収納で暮らしが快適になる「ローズビレッジ宝殿駅前Ⅵ」のモデルハウスの間取りをご紹介しました。
ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひご見学にお越しくださいね。
ご来場をお待ちしております!
▼モデルハウス情報はこちら▼
https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/4takasago/rv_hodenekimae6/
※本記事は2024年6月現在の情報に基づいて作成されたものです。各分譲地の最新情報につきましては、公式HPをご確認ください。

高騰し続ける光熱費や省エネ意識の向上を背景に、住宅の断熱性能に対する関心が急速に高まっています。
そんな状況の中、住宅の断熱性や省エネ性に関わる「HEAT20」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。HEAT20は、ZEH住宅や長期優良住宅を上回る断熱性能を示す基準であり、G1~G3のグレードに区分されています。
この記事では、あらためてHEAT20を解説したうえで、G2グレードを目指すメリットをお伝えします。HEAT20は今後の家づくりで必須ともいえる情報です!ぜひ参考にしてください。
ZEHを超える断熱性「HEAT20 G2」とは?

HEAT(ヒート)20とは「一般社団法人20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」の略称です。HEAT20では、日本を8つの地域に区分し、それぞれの地域に適した断熱性能の基準を定めています。HEAT20は民間基準ですが、国が定める省エネ基準よりもエネルギー削減率が高く、「ZEH(ゼッチ)」など主要な省エネ住宅以上の断熱性能を求められることから、今後目指すべき基準として大きく注目されています。
今、HEAT20が注目されているワケ

HEAT20の基準が定められた背景には、日本住宅の断熱性能が諸外国と比べ非常に低レベルという事実がありました。2018年時点の既存住宅では、現行の省エネ基準を満たす住宅は11%のみ。なんと、9割近くもの住宅が十分な断熱性を持たず、さらに全体の3割は無断熱という結果でした。
しかも、現行の省エネ基準はそもそも高レベルとは言えず、ドイツの「パッシブハウス基準」に比べると省エネ性(年間のエネルギー燃費)は約7倍の開きがあります。
2025年度からは現行基準を超える断熱性や省エネ性を設けることが義務化されますが、それでも十分とはいえません。
HEAT20では、家の中で暑さ寒さを我慢することなく、快適で省エネに暮らすために必要な高断熱の指標を独自につくり、普及を目指してきたことが評価され、現在大きく注目される結果に至りました。
参考:国土交通省|脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会 説明資料
断熱性能を判断する地域区分と基準
各地域における断熱性能は、UA値という数値や、8つに区分された該当エリアの組み合わせで判断されます。
UA値:室内の熱が外部へどのくらい逃げやすいかを示す数値。値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性が高いことを示す。
国の省エネ基準に則る「断熱等級」とHEAT20のUA値ですが、各地域において必要とされる数値は以下の通りです。
| 地域区分 | 1・2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 代表都市 | 札幌 | 盛岡 | 松本 | 宇都宮 | 東京 | 鹿児島 | 那覇 |
| HEAT20 G3 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | - |
| 等級7 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | - |
| HEAT20 G2 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | - |
| 等級6 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | - |
| HEAT20 G1 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | - |
| 等級5 ※2030年度義務化 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | - |
| ZEH | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | - |
| 等級4 ※2025年度義務化 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | - |
HEAT20 G1・G2・G3の断熱レベルの違い
HEAT20ではG1からG3までの基準が定められており、地域ごとのUA値は前項で示した通りですが、より実感しやすいのは室温の違いです。G1からG3の定める基準は、住まいの健康を目的として、室内の温度ムラを小さくし、暮らしやすさ向上や温度ストレスを考慮して設定されています。
| 1・2地域 | 3~6地域 | 7地域 | |
| HEAT20 G3 | 概ね16℃を下回らない | 概ね15℃を下回らない | 概ね16℃を下回らない |
| HEAT20 G2 | 概ね15℃を下回らない | 概ね13℃を下回らない | |
| HEAT20 G1 | 概ね13℃を下回らない | 概ね10℃を下回らない | |
| 省エネ基準(等級4) | 概ね10℃を下回らない | 概ね8℃を下回らない | |
「HEAT20 G2」のメリット

G1グレードでもZEH住宅などの水準を超える断熱性能が期待できますが、今後の家づくりで目指すべきはG2グレードです。ここでは、HEAT20 G2グレードのメリットをお伝えします。
1年中過ごしやすい家になる

G2グレードの基準をクリアした家は、ZEH住宅や長期優良住宅と言った省エネ住宅の性能を大きく超える断熱性が期待できます。季節による温度差の激しい本州でも、室温を一定に保ち季節を通して快適に過ごすことができます。
冬季の最低室温も13~15℃に保つことができるため、急激な温度差によって引き起こされるヒートショックのリスク軽減が期待できるでしょう。
光熱費を削減できる

外気温の影響を受けにくい高断熱仕様により、冷暖房効率を上げ大幅に光熱費を削減します。光熱費が上がり続ける現在、特に期待すべきメリットと言えるでしょう。
また、G3グレードほどに断熱対策への初期投資がかからないため、コストバランスが良い点も魅力のひとつです。
人と家の健康に貢献する

断熱性の低い家は、外壁や窓部分における室内外の温度差が激しく、結露やカビが発生しやすくなります。住宅の結露やカビは、アレルギーや喘息の原因となるだけでなく、建物の主要な構造体を腐食させる原因となります。
G2グレードの住宅では、内・外への断熱材や樹脂サッシのLow-Eペアガラスなど、高断熱基準をクリアするための高性能な建材が採用されます。高い断熱仕様により、結露やカビの発生を防ぎ、人と家の健康を長期的に守る住まいとなるのです。
購入時に補助金が活用できる

HEAT20に対する補助金制度はありませんが、G2グレードは国の定める「ZEH+ハイグレード仕様」の断熱性能を満たすため、基本的なZEHの条件をクリアすれば補助金の対象になる可能性があります。さらに、メンテナンス計画や構造計算の実施などの条件を満たすことで、長期優良住宅を対象とする補助金を受けることも可能です。
▼2024年度 ZEH住宅に対する補助金事業についてはこちら▼
https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/company_blog/2024年度zeh補助金受付開始!ヤング開発「heat20%e3%80%80g2グレー/
なお、ヤング開発の「HEAT20 G2グレード」仕様なら補助金最大125万円が受け取れます!
今後の家づくりはHEAT20を基準に

HEAT20の基準で建てられた住宅は、少ないエネルギー消費でも快適に過ごせ、光熱費の大幅な削減が期待できます。
未だ断熱性や省エネ性については発展途上と言える日本の住宅業界ですが、HEAT20の考え方は今後広く浸透していくものと思われます。
この先何十年も暮らしていくマイホームを建てるならば、最低でも2030年に義務化が予定されている断熱等級5以上の性能を、さらなる快適性と省エネ性を得たいならばHEAT20 G2グレードの性能を確保するのがおすすめです。
ヤング開発なら「HEAT20 G2グレード」仕様を無料で選べる!

今回は、今後目指すべき住まいの断熱性能「HEAT20 G2」グレードについてお伝えしました。
兵庫を拠点に家づくりを手掛けるヤング開発では、標準仕様でZEH住宅を提供しているだけでなく、選べる無料標準としてHEAT20 G2グレードを設定しています。
G2グレードをお選びいただけば、ZEH支援制度における「ZEH+」の100万円、追加補助の「ハイグレード仕様」25万円、計125万円が受給できます!
高断熱・省エネの家づくりをご検討の方は、ヤング開発までお気軽にご相談ください。
※補助制度の内容は2024年5月現在の情報に基づき作成したものです。最新の情報は、各制度の公式ホームページでご確認ください。
こんにちは、ヤング開発です。
ジメジメとした天気の続く梅雨の時期は、洗濯物が乾きにくかったり、カビが生えやすかったりという悩ましい問題が多いものです。
長引く湿気は住まいにも住む人の健康にも悪影響を与えてしまうため、何とか対策を講じたいところ。

今回は、梅雨時期における特有のお悩みを解決する住宅設備をまとめてご紹介します!
住まいにおけるさまざまな工夫で、不快な季節を軽やかに乗り越えましょう♪
●浴室暖房乾燥機

室内干しを検討する際、ぜひ活用したいのが浴室暖房乾燥機です。
浴室はそもそも防水処理がされているため、湿気を外に逃がさず効率的に洗濯物を乾燥させます。
暖かい送風によって、洗濯物が早く乾きやすいのも嬉しいポイント。
雑菌の繁殖が抑えられ、嫌な生乾き臭も発生しにくくなります。
●ランドリールーム

洗濯物を洗う・干す・取り込む・たたむという作業がまとめて行えるランドリールームは、家事効率がアップする間取りとして近年人気が高まっています。
ベランダまでの移動が必要なく、花粉や梅雨時期、夜間でも洗濯物ができるため、共働きの忙しいご家庭にピッタリのスペースです。
●室内干しユニット

天井や壁に取り付け、室内でも洗濯物干しが可能になる室内干しユニットは、定番の「ホスクリーン」を筆頭に、使わない時は格納できるタイプなどさまざまな製品が展開されています。
ランドリールームや洗面室だけでなく、リビングの近くや2階ホールなどに設置するケースも多く、ライフスタイルにマッチする使い勝手の良さが魅力です。
●機能性壁材

自然に心地いい湿度に調整しながら気になるニオイも脱臭してくれる素材として、機能性壁材が挙げられます。
タイル状壁材の「エコカラット」は、機能性とデザイン性を兼ね備えアクセントウォールへ採用するケースも多く見られます。
また、壁紙でも防臭効果や防カビ効果、吸放湿効果などの高機能タイプが多彩に展開されています。
ジメジメとした梅雨時期の湿気は日本で暮らす限り避けられないものですが、あらゆる工夫で過ごしやすい住まいをつくることは可能です。
外環境に影響されない家づくりで、いつでも家事がしやすい快適なマイホームを目指しましょう。
こんにちは、ヤング開発です。
2023年初めから開始された政府の「激変緩和措置」である電気代・ガス代の負担軽減策は、2024年5月使用分で終了し、6月以降は補助がなくなる予定です。
これからは光熱費の高騰が家計を直撃し、ますますランニングコストの負担が重くなっていくことが予想されます。

今後の家づくりでは光熱費の負担軽減への対策が必要不可欠となりますが、そんな中でおすすめしたいのが「ZEH住宅」です。
今回は、光熱費を気にしない暮らしを実現するZEH住宅の魅力をお伝えします。
●電気代・ガス代の激変緩和措置はいつまで?
2023年1月からスタートした「電気・ガス価格激変緩和対策事業」いわゆる激変緩和措置は、エネルギー価格高騰による家庭や企業の負担を軽減するため政府が料金の一部を補助する政策です。
2024年も継続されていましたが、2024年5月使用(6月検針)分を持って終了することが発表されました。
政策終了後は、再び光熱費の高騰が避けられない状況となります!
●消費エネルギー実質ゼロにするZEH住宅の魅力とは
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)住宅は、使うエネルギーと創るエネルギーの組み合わせによりエネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指した住宅です。
以下のメリットを持つことで、光熱費の大幅な削減だけでなく、住まいの快適性や安全性を実現するのがZEH住宅の魅力と言えるでしょう。
・光熱費の削減につながる
・少ない消費電力で1年中快適な室内温度を実現する
・災害時に電気が使える
・不動産としての価値がアップする
●ヤング開発は全戸ZEH標準!

ヤング開発の家は、全戸においてZEH住宅を標準仕様としています。
最新式の太陽光発電システムや、エコキュート付きオール電化仕様、超高性能断熱材などがすべて標準装備!
さらに、ZEHを超える性能を持つ「HEAT20 G2」グレード仕様が無料標準で選択可能です。
光熱費高騰に従い、今後ますます需要が高まっていくと予想されるZEH住宅。
ZEH仕様のマイホーム購入をご検討の方は、ぜひヤング開発までお気軽にご相談ください。
こんにちは、ヤング開発です。
今回は、高砂市のI様邸にお邪魔し、思い出に残るエピソードやお気に入りポイント、住み心地などをお伺いしました。

Q.家を買おうと思ったきっかけは?
もともと住んでいた賃貸の部屋は日当たりや住み心地に不満がありました。
子どもが産まれて狭さを感じ始めたこともあり、家を建てようと決意しました。
Q.ヤング開発とこの分譲地を選んだ理由は?
ヤング開発は高砂で知名度があり、名前はよく聞いたことがありました。
会社から近く広い敷地の分譲地を探していたところ、ヤング開発で希望に合う分譲地があったのでここに決めました。

Q.こだわったところやお気に入りポイントについて教えて!
とにかく広さにはこだわりました。
リビングや玄関、お風呂、脱衣所など、全体的に広くしたかったのでメーターモジュールで建ててもらいました。

天井高も2.7mと高めにして、かなり満足しています。
家に来た人には「明るくて広い家やね~」「部屋数が多いな~」とよく言われますね。

主人が仕事で夜勤や朝早いときがあるのですが、リビングや寝室を通らなくても身支度が一通りできるように、玄関からも洗面室からも出入りできるランドリールームを配置しました。
洗濯物を乾燥機から出して、そのままハンガーにかけ、すぐに着られる点も便利です。

玄関は広めに作ってもらいました。
靴の脱ぎ履きもしやすく、ベビーカーもそのまま乗り入れられるので満足しています。
Q.設備や性能はどうですか?
太陽光発電にして、かなり電気代が安くなったと感じています。
夏でも一万円切るくらいなので、だいぶ助かっています。
食洗機があるので洗い物にかける時間がだいぶ短くなって、その分子どもと遊ぶ時間がとれるなど、他のことに時間を使えるようになって良かったと思います。

Q.やって良かったこと、今後楽しみなことは?
やって良かったのは、トイレを2つにしたことと、玄関入ってすぐのところに洗面台を設けたことですね。
玄関すぐの洗面台は、子どもが汚れて帰ってきてもすぐ手を洗えますし、お友だちが来てくれた時も家に上がるタイミングで手洗いができて便利です。

駐車場の奥に庭があるのですが、今後は人工芝にしてみたり、石を敷き詰めてみたり、いろいろやれることがあると思うので楽しみです。

I様、どうもありがとうございました!
新居でご家族仲良くお幸せにお過ごしくださいね!
▼I様のインタビューは動画でもご覧いただけます▼
https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/voice/vol.65.htm
▼【お客様の声】一覧はこちら▼

家づくりを検討する方なら、幾度か耳にするであろう「エコ住宅」という言葉。
何となくイメージが付くものの、具体的にはどのような家なのかわからない、と感じる方が多いのではないでしょうか。
この記事では、エコ住宅の基準や条件、そのメリットや注意点を解説します。
普及率が高まるZEH住宅や長期優良住宅など、エコ住宅の種類についても紹介。マイホームを検討する方は、ぜひ参考にしてください。
エコ住宅とは

エコ住宅は、断熱性などの住宅性能を高めることで、消費エネルギーを抑えながら快適な室内環境をつくる「人にも環境にもやさしい家」です。
具体的な内容を紹介していきましょう。
エコ住宅ってどんな家?その基準と条件
エコ住宅は、気密性や断熱性、耐震性や耐火性を高めることにより、外環境の影響を受けにくく高耐久になるように作られています。一般的な住宅に比べ冷暖房効率が良く、少ない電力でも家中を快適な温度に整えることが可能です。
光熱費を抑えながら1年中快適に過ごせるため、長期的なコストパフォーマンスに優れ、ヒートショックといった温度差に起因する健康被害のリスクも減らせます。
このエコ住宅、実は明確な定義や基準は存在しません。
ただし、エコ住宅であるかどうかの判断基準のベースとなるものに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」があります。
この法律の改正により、2025年度以降はすべての新築住宅において「省エネ基準」への適合が義務化されます。
省エネ基準適合のためには、大まかに以下2点の基準を満たすことが必要なため、エコ住宅であるかどうかを判断する際には、これらの基準を超える性能を持つかをチェックするのが有効です。
・断熱等性能等級(断熱等級) 4以上
・一次エネルギー消費量等級(一時エネ等級) 4以上
エコ住宅と省エネ住宅の違いは?

エコ住宅と類似する言葉に「省エネ住宅」や「エコハウス」というものがあります。
エコ住宅はそもそも包括的な意味合いがある言葉のため、どちらも同義に使われるケースがありますが、経済産業省と環境省ではそれぞれの住宅について以下のようにまとめています。
【省エネ住宅(省エネルギー住宅)】
「断熱」「日射遮蔽」「気密」により、以下の内容を実現する家
冬:部屋の中の暖かい空気が逃げず、部屋内や部屋間の室温がほぼ均一。北側の風呂もトイレも寒くなく、結露もしない。
夏:室外からの熱気が入らずに涼しい。小型のエアコンでも良く効き、朝・夕は風通しが良い。
参考:経済産業省|省エネ住宅
【エコハウス】
地域の気候風土や敷地の条件を十分に活かしながら、自然エネルギーを最大限に活かし、さらに身近に手に入る地域の材料を使うなど、環境に負担をかけない方法で建てられた家。
「断熱」「気密」「日射遮蔽」「日射導入」「蓄熱」「通風」「換気」「自然素材」の8つの環境基本性能が実践され、住まいに必要なエネルギーを最小限に抑えた快適な住宅を指す。
参考:環境省|エコハウスとは
エコ住宅を選ぶメリットと注意点

エコ住宅には多くのメリットがありますが、建築・購入する際にはいくつかの注意点もあります。
エコ住宅のメリット
・温度差の少ない快適な室内環境が実現する
・光熱費を抑えられる
・災害に強い家になる
・家の長寿命化が図れる
・条件により補助金を受け取れる
エコ住宅のメリットは、何といっても快適な住まい環境と低いランニングコストを実現できる点でしょう。
また耐震性や耐久性へも配慮されているため、地震や台風といった災害、シロアリやカビによる腐蝕にも強く、長持ちする住まいが実現します。結果として、大規模改修といったメンテナンスが必要なくなるもの嬉しいポイント。
ZEH(ゼッチ)住宅や長期優良住宅などの認定を受ければ、購入時に補助金を受け取れる可能性もあります。
エコ住宅の注意点

・性能や導入設備によっては建築費用が高くなる
・施工業者により品質にムラが出る
エコ住宅は、断熱材や窓サッシといった建材、太陽光発電システムや蓄電池などの設備の仕様や有無によって費用に大きな差が生じます。家を建てる地域の気候やライフスタイルに合わせて、最適な性能レベルを確保することが大切です。
また、エコ住宅は近年急速に普及が進んでいることもあり、経験不足の施工業者も存在するのが実情です。特殊な仕様のエコ住宅の設計や施工には正しい知識と経験が必要不可欠。さらに認定や補助金申請の手続きは煩雑な内容のものも多いため、豊富な実績を持つ会社に依頼することが、スムーズに家づくりを進めるポイントになります。
エコ住宅の種類

エコ住宅にはいくつか種類があり、それぞれで特化する内容や基準が異なります。
省エネ基準適合住宅
2025年度以降すべての新築住宅に義務化される省エネ基準をクリアした住宅です。
一般的な既存住宅に比べれば高い省エネ性能を持ちますが、今後は家づくりでは最低レベルとなるエコ住宅の水準です。
ZEH住宅

ZEH住宅は、高断熱・高気密の外皮によってエネルギー消費を抑えながら、太陽光発電システムなどの創エネ設備を組み合わせることで、年間の一次エネルギー消費量を概ねゼロにする住宅です。
国の補助金制度などにより普及が拡大し、標準仕様とする住宅会社も増えてきました。
長期優良住宅

長期優良住宅は、省エネ性に加え耐震性や劣化対策、住みやすさやバリアフリー性など、さまざまな要件の達成が求められる国の認定住宅です。
維持管理や保全に関する計画立案も要件に含まれ、適切にメンテナンスを行った場合の期待耐用年数は100年超とされています。
ZEH住宅以上に税制措置や補助金の優遇を手厚く受けられます。
認定低炭素住宅
認定低炭素住宅は、CO2の排出を抑えるための対策に特化した環境配慮型の住宅です。
原則として市街化区域に建てられた住宅が対象で、建築の劣化対策に加え、節水型機器やエネルギー消費を管理するHEMSの導入、住宅と電気自動車間で給電・充電するV2Hの設置などが求められます。
パッシブハウス
「究極のエコハウス」とも呼ばれるパッシブハウスは、自然エネルギーを最大限活用するエコ住宅です。非常に厳しいエネルギー消費基準が設けられ、年間の日射や通風、建物の蓄熱性能といった条件を考慮した厳密な設計が必要なため、実施できる建築士も限られています。
まとめ

エコ住宅は明確な基準や条件がなく、実際の住宅性能もハウスメーカーや工務店によってさまざまです。
エコ住宅の省エネ性能を判断する際には「省エネ基準」を超える性能であるかどうかをチェックしましょう。
また、エコ住宅にはさまざまな住宅タイプがあります。
「光熱費を最小限に抑えたいならZEH住宅」
「次世代まで引き継げる家づくりをしたいなら長期優良住宅」
以上のように、家族の考え方や予算に合わせてエコ住宅のタイプを選ぶことが大切です。また、要件をクリアすれば一軒の家で複数の認定を受けることも可能です。ただし手続きには追加費用がかかるケースが多いため、必要に応じて検討しましょう。
新築住宅35,000戸の実績を持つヤング開発では、全戸ZEH住宅を標準仕様としています。さらに、国内最高レベルの断熱性能を持つ「HEAT20 G2」グレードが標準仕様でセレクト可能です。
デザインも住み心地も妥協なしのエコ住宅なら、ヤング開発にぜひお任せください。
2025年4月 (1)
2025年3月 (8)
2025年2月 (11)
2025年1月 (10)
2024年12月 (11)
2024年11月 (10)
2024年10月 (10)
2024年9月 (9)
2024年8月 (10)
2024年7月 (9)
2024年6月 (12)
2024年5月 (21)
2024年4月 (9)
2024年3月 (8)
2024年2月 (8)
2024年1月 (9)
2023年12月 (9)
2023年11月 (8)
2023年10月 (10)
2023年9月 (10)
2023年8月 (8)
2023年7月 (8)
2023年6月 (10)
2023年5月 (7)
2023年4月 (9)
2023年3月 (9)
2023年2月 (9)
2023年1月 (9)
2022年12月 (11)
2022年11月 (8)
2022年10月 (8)
2022年9月 (9)
2022年8月 (7)
2022年7月 (8)
2022年6月 (7)
2022年5月 (8)
2022年4月 (8)
2022年3月 (8)
2022年2月 (8)
2022年1月 (8)
2021年12月 (8)
2021年11月 (7)
2021年10月 (7)
2021年9月 (8)
2021年8月 (8)
2021年7月 (8)
2021年6月 (8)
2021年5月 (8)
2021年4月 (8)
2021年3月 (7)
2021年2月 (8)
2021年1月 (8)
2020年12月 (8)
2020年11月 (8)
2020年10月 (7)
2020年9月 (8)
2020年8月 (8)
2020年7月 (8)
2020年6月 (8)
2020年5月 (9)
2020年4月 (8)
2020年3月 (8)
2020年2月 (8)
2020年1月 (8)
2019年12月 (8)
2019年11月 (8)
2019年10月 (8)
2019年9月 (8)
2019年8月 (8)
2019年7月 (8)
2019年6月 (8)
2019年5月 (8)
2019年4月 (8)
2019年3月 (8)
2019年2月 (8)
2019年1月 (8)
2018年12月 (8)